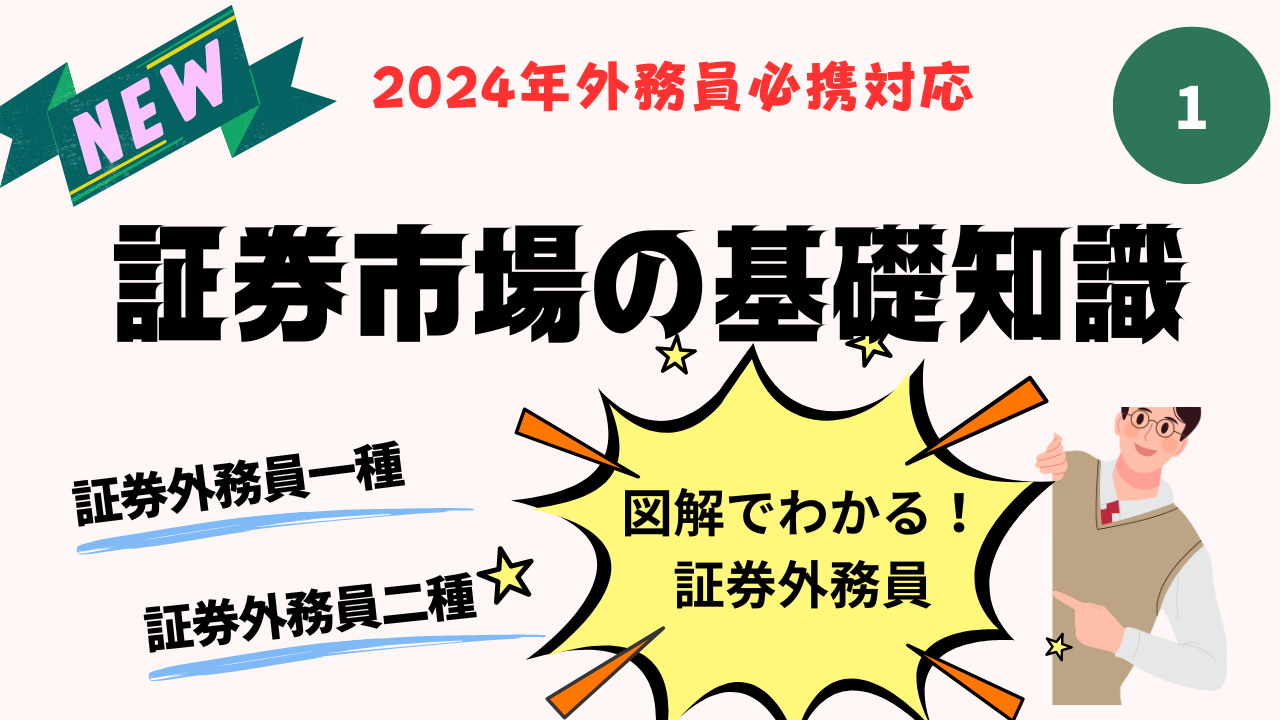証券市場
直接金融と間接金融
金融とは、資金に余裕のある方が資金を必要としている方に金銭を移転することをいい、直接金融と間接金融の2つに分けることができます。
間接金融は、資金の提供者(預金者)が銀行等の金融機関に金銭を預け入れ、その預け入れた金銭を銀行等の金融機関が企業等に貸し出すことで資金の移転がなされます。間接金融では、貸し出した資金の回収リスクは、金融機関が負うことになります。
直接金融は、資金の調達を検討している企業などが、株式や債券などの有価証券を発行し、資金の提供者(投資家)が、それらの有価証券を直接購入することで資金の移転がなされます。有価証券の発行会社が倒産等した場合、発行された株式や債券の価値はなくなります。そのようなリスクは、資金の提供者である投資家が負うことになります。
発行市場と流通市場
直接金融において、資金調達を目的として有価証券(株式や債券など)を新規に発行し、直接、資金提供者(投資家)に第1次取得される市場のことを発行市場(プライマリーマーケット)といい、すでに発行された有価証券が、第1次取得者から第2次取得者そして第3次取得者へと転々と流通される市場のことを流通市場(セカンダリーマーケット)といいます。
有価証券の第1次取得者が、取得した有価証券を処分(換金)するためには、流通市場が必要となります。また、発行市場における有価証券の発行価格の基準となるのは、流通市場で売買されている価格になりますので、発行市場と流通市場は、密接な関係があり、有機的に結びついています。
規制機関
自主規制機関
直接金融が成り立つためには、健全な市場が形成されていなければなりません。そのために市場を構成する各団体が自主的に規則を作り、市場の健全化を図っています。それらの団体は、自主規制機関と言われ、金融商品取引所、日本証券業協会及び投資信託協会などがあり、金融商品取引法により、自主規制機関としての性格(権限)を付与されています。
公的規制機関
自主規制機関に対して、証券取引等監視委員会は、金融庁に属する公的機関です。インサイダー取引や証券会社等における不公正取引行為についての強制調査権があります。また、自主規制機関等における取引ルールが適切に行われているかを確認するための立入検査権等が付与されています。
その他の証券関係機関
投資者保護基金
投資者保護基金は、金融商品取引業者(証券会社など)の経営破綻によって、金銭及び有価証券を預け入れている顧客の被る損失の補償を目的とした基金です。基金の会員となる者は、金融商品取引業者のみであり、第一種金融商品取引業者は、必ずいずれか1つの基金に加入しなければなりません。
投資者保護基金は、金融商品取引業者(証券会社など)の経営破綻によって、金銭及び有価証券を預け入れている顧客の被る損失の補償を目的とした基金となっており、金融商品取引業者が経営破綻した場合、顧客1人あたり1,000万円まで補償されます。ただし、機関投資家(保険会社や年金基金などの大口の投資家)、国および地方自治体などは投資者保護基金の補償対象から除かれます。
証券保管振替機構
証券保管振替機構は、国債以外の有価証券の決済及び管理業務を集中的に行う日本で唯一の証券決済機関です。株式、社債、投資信託といった有価証券の振替業務を運営しています。