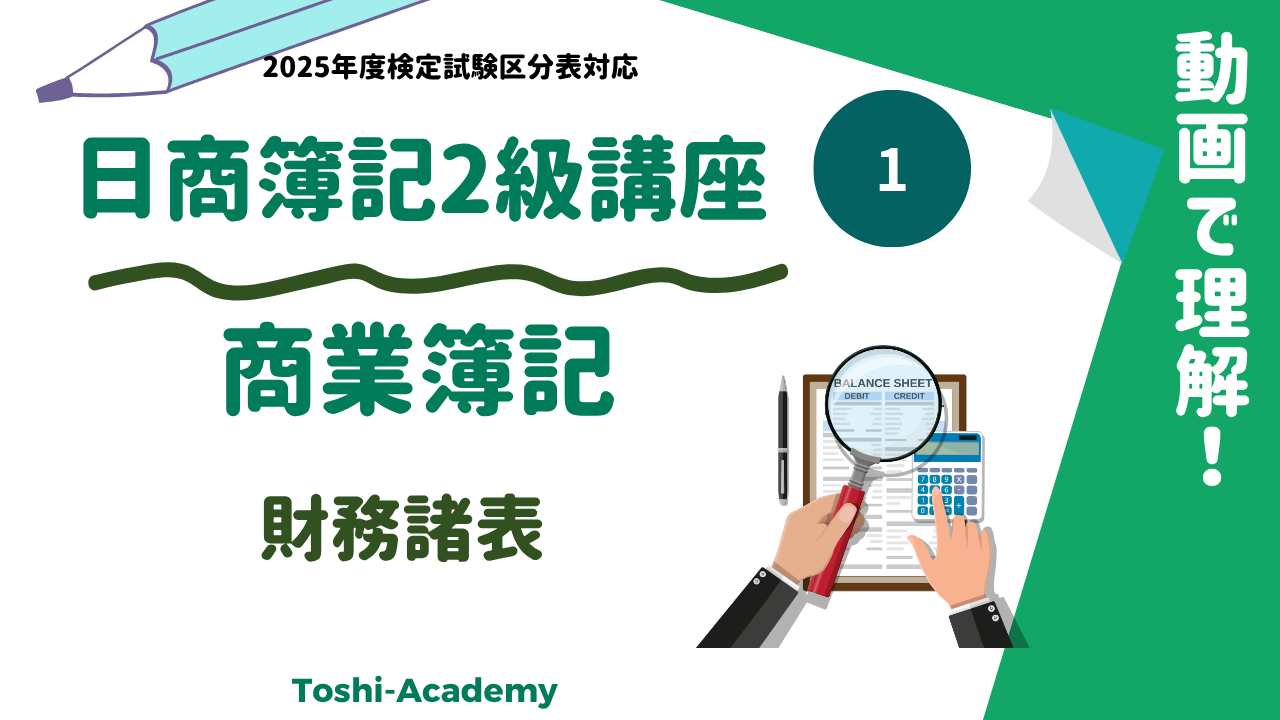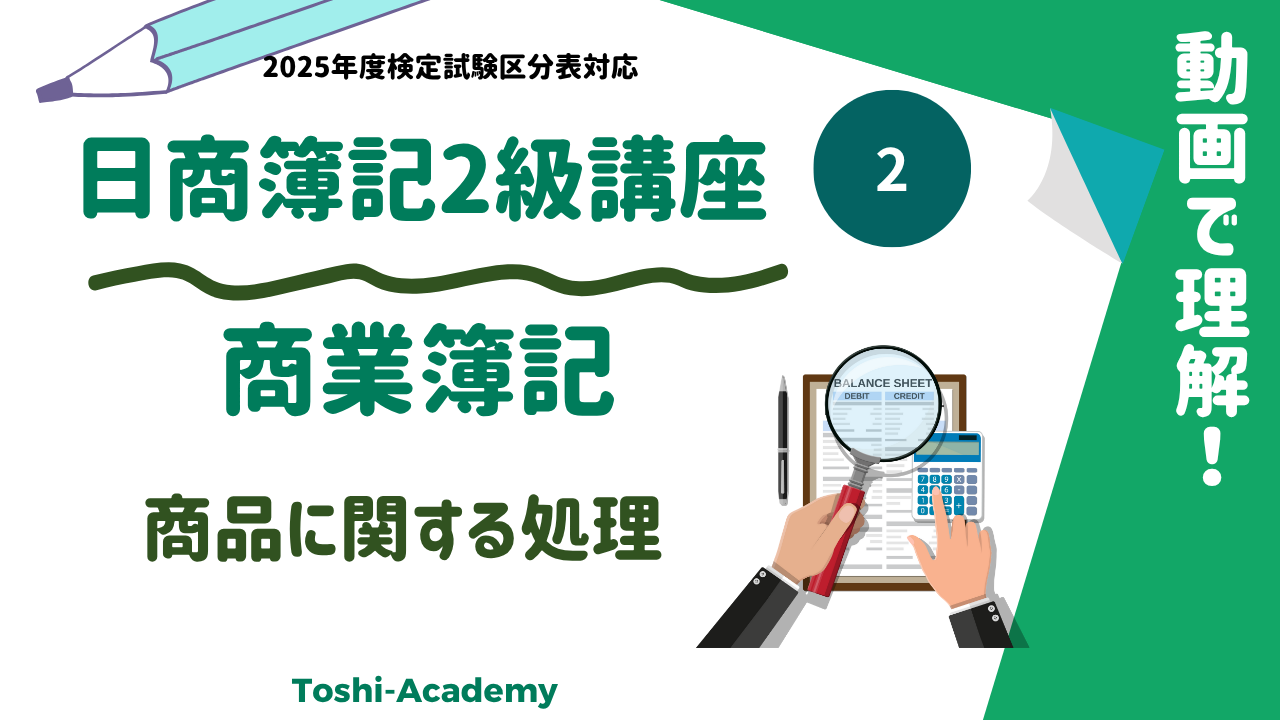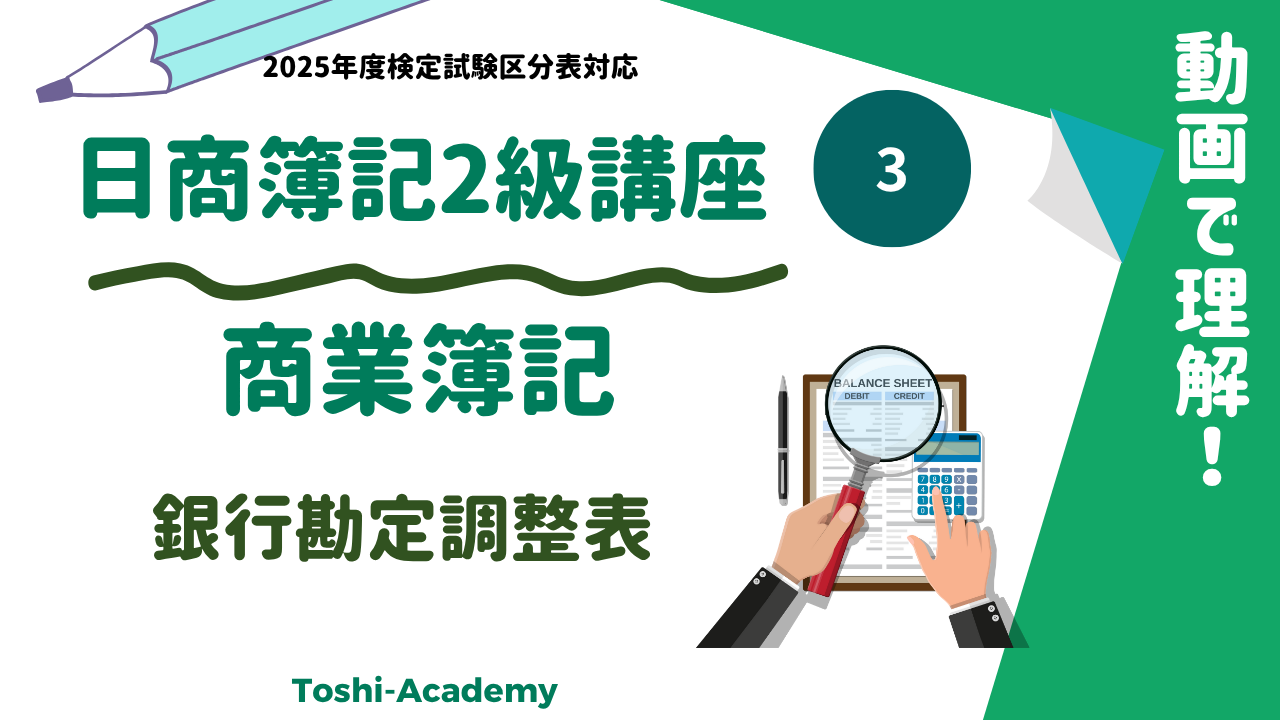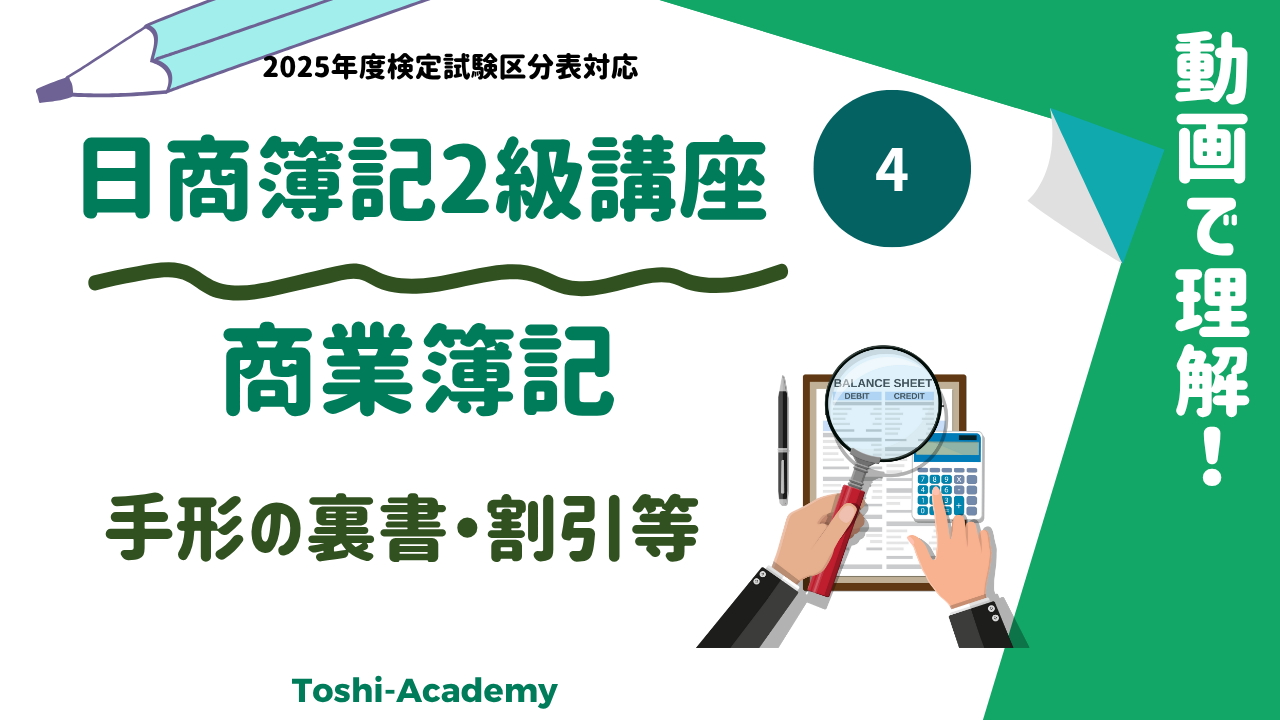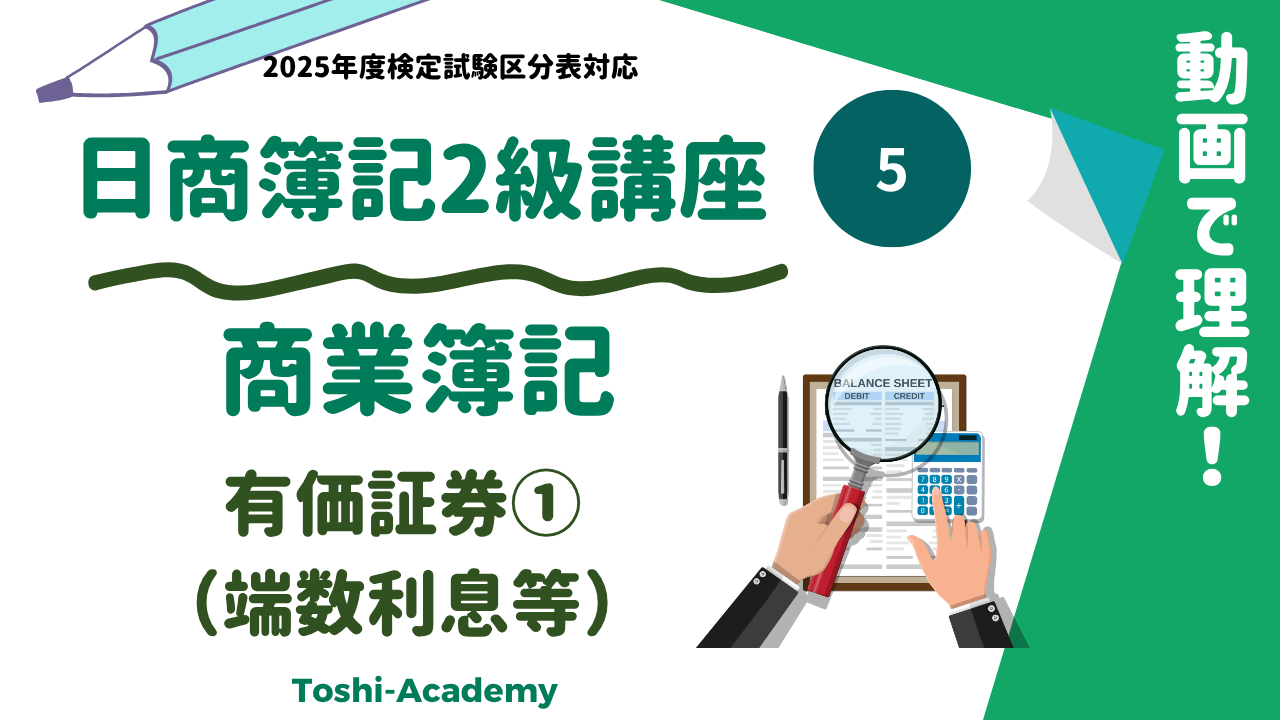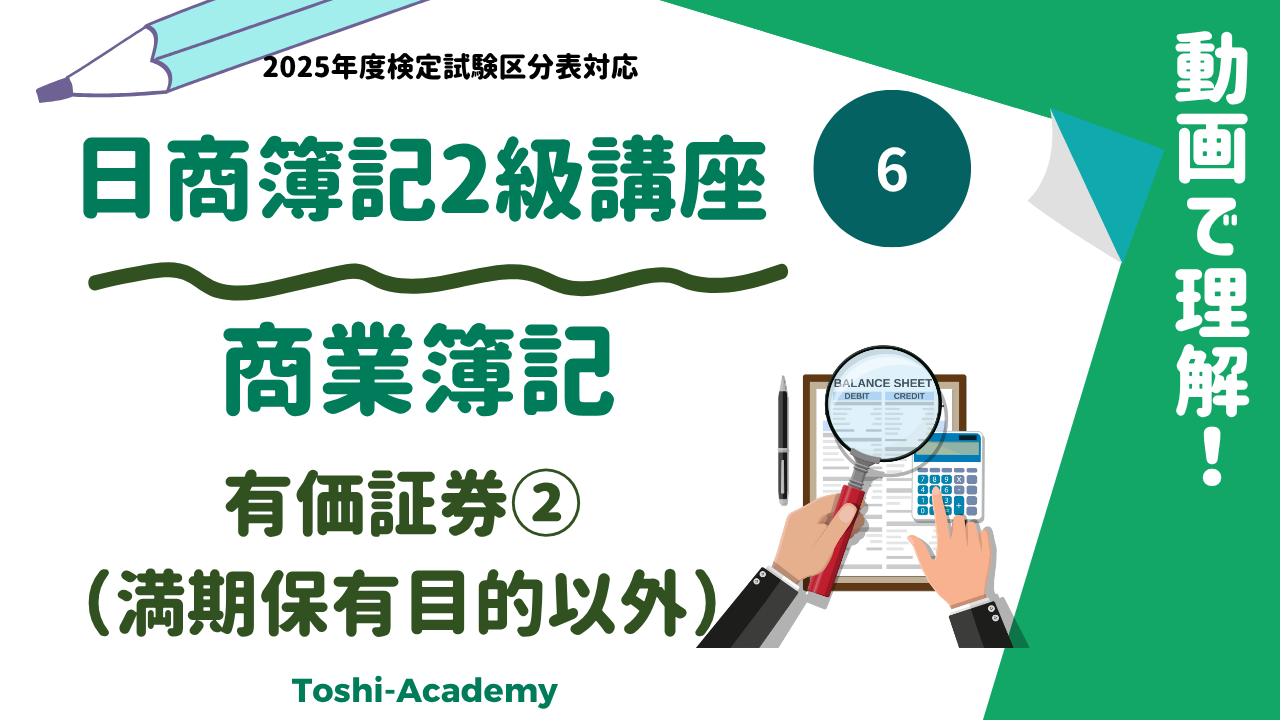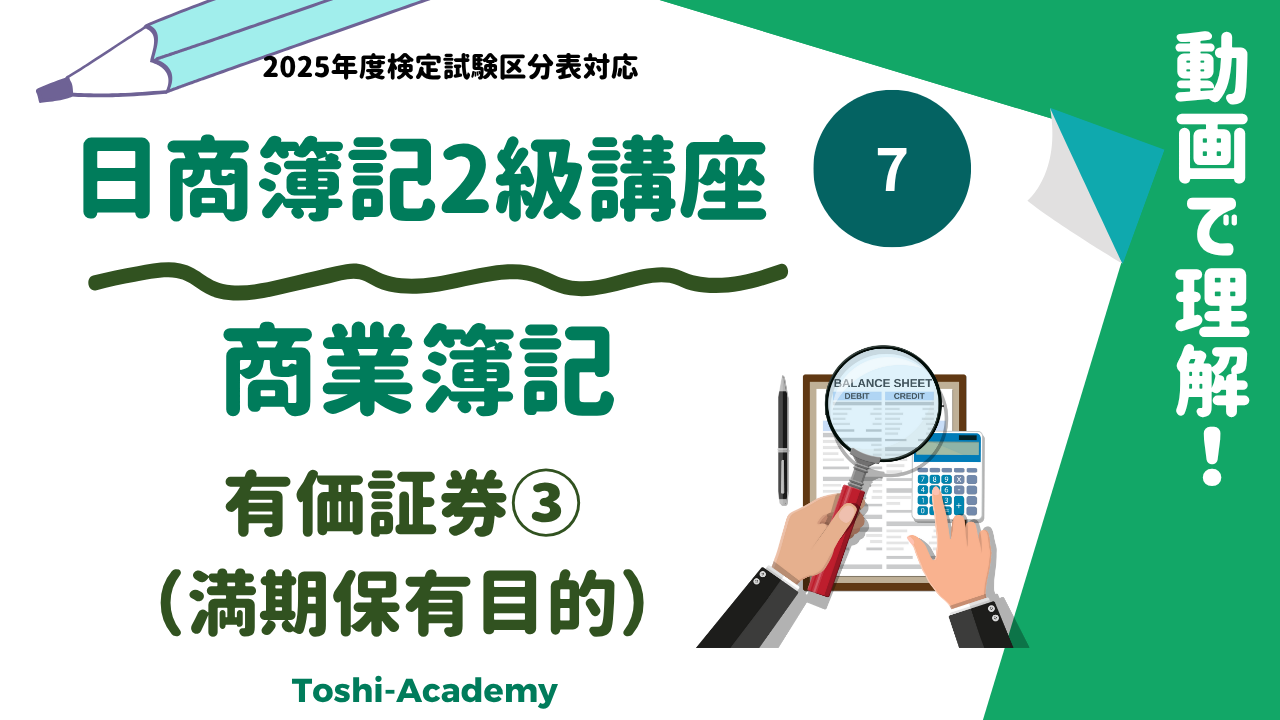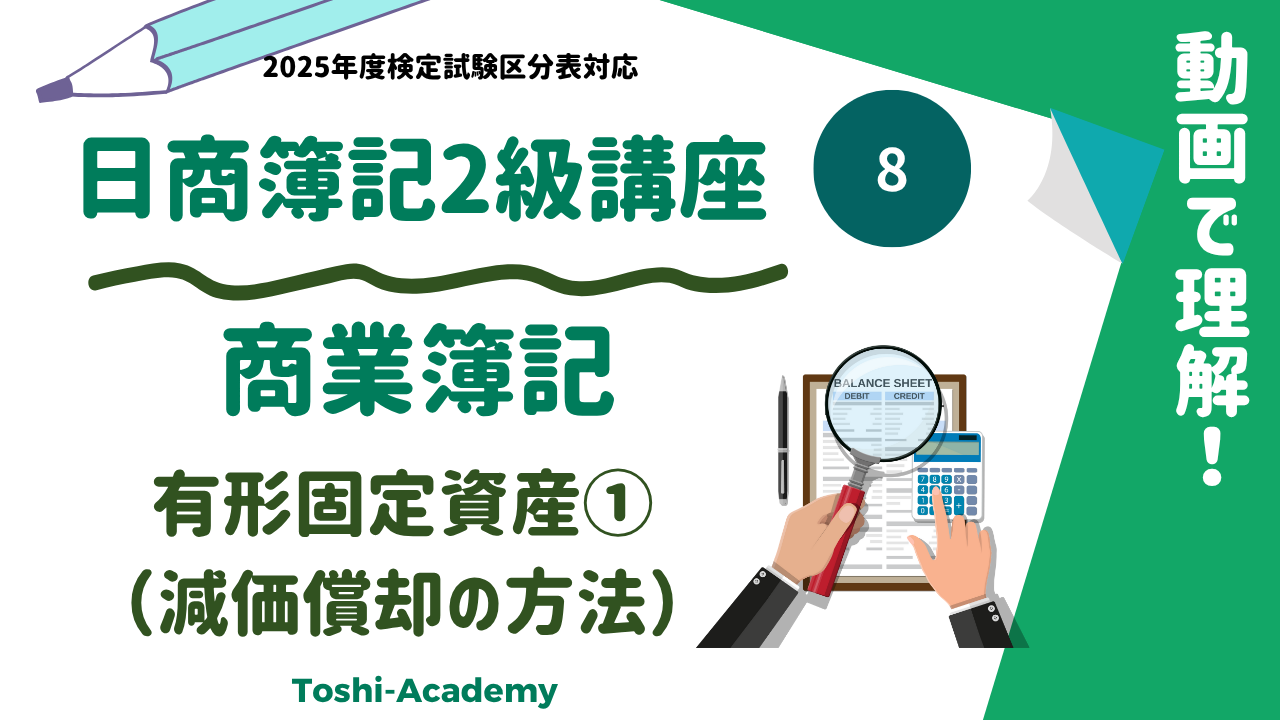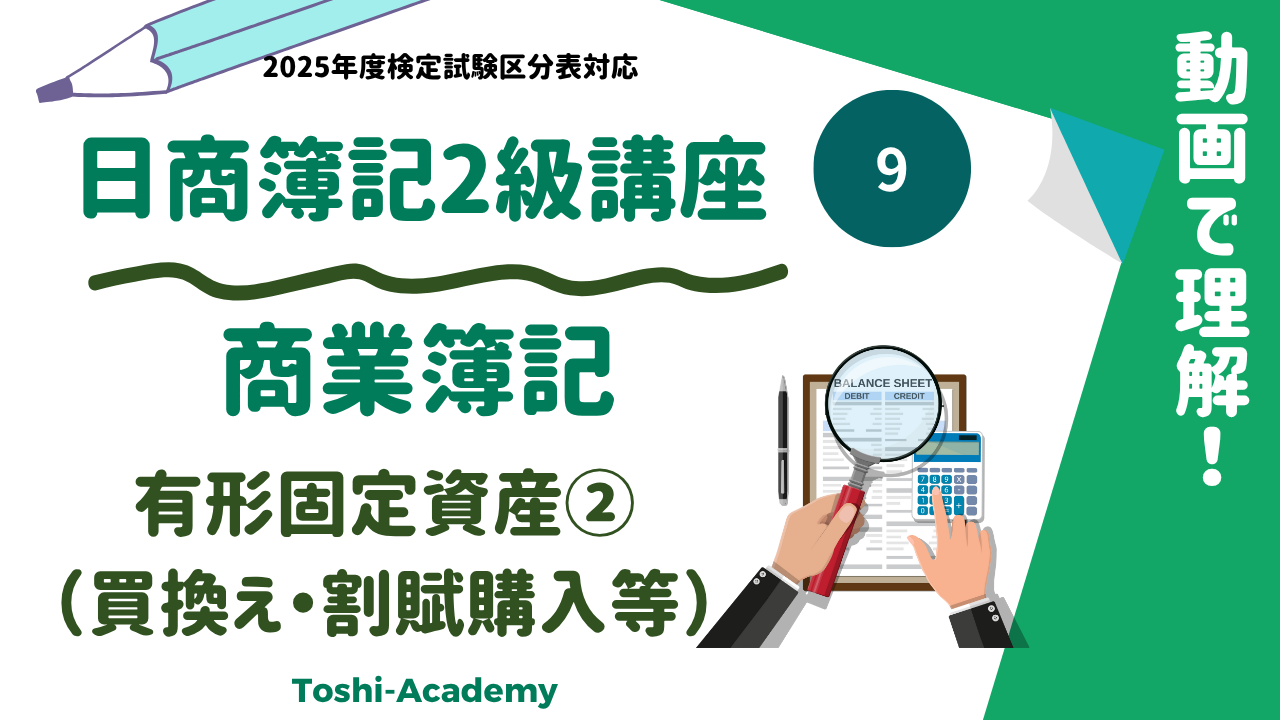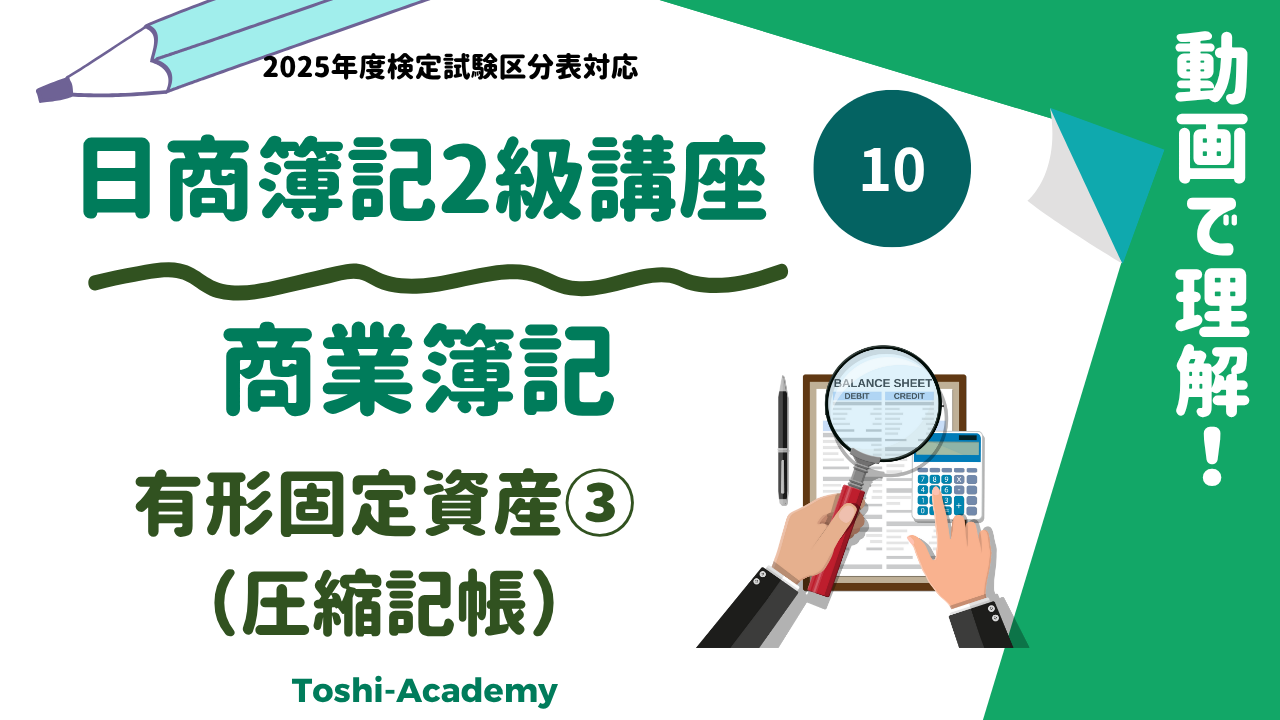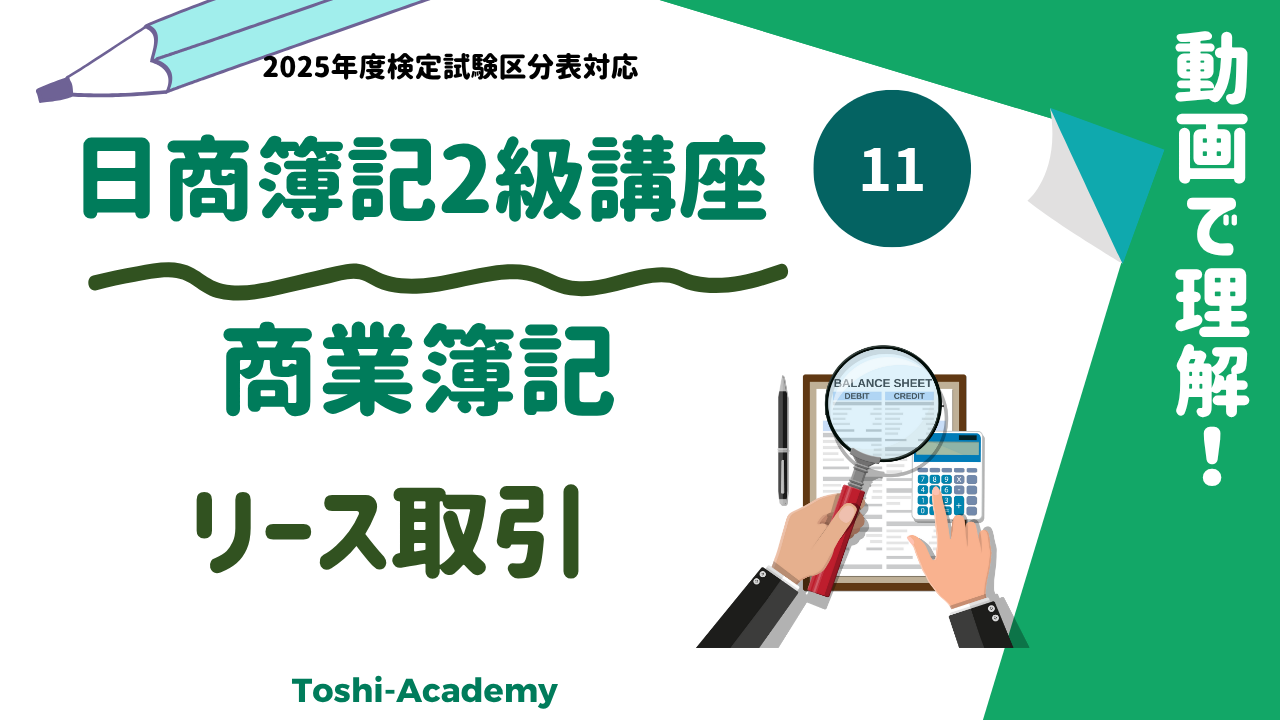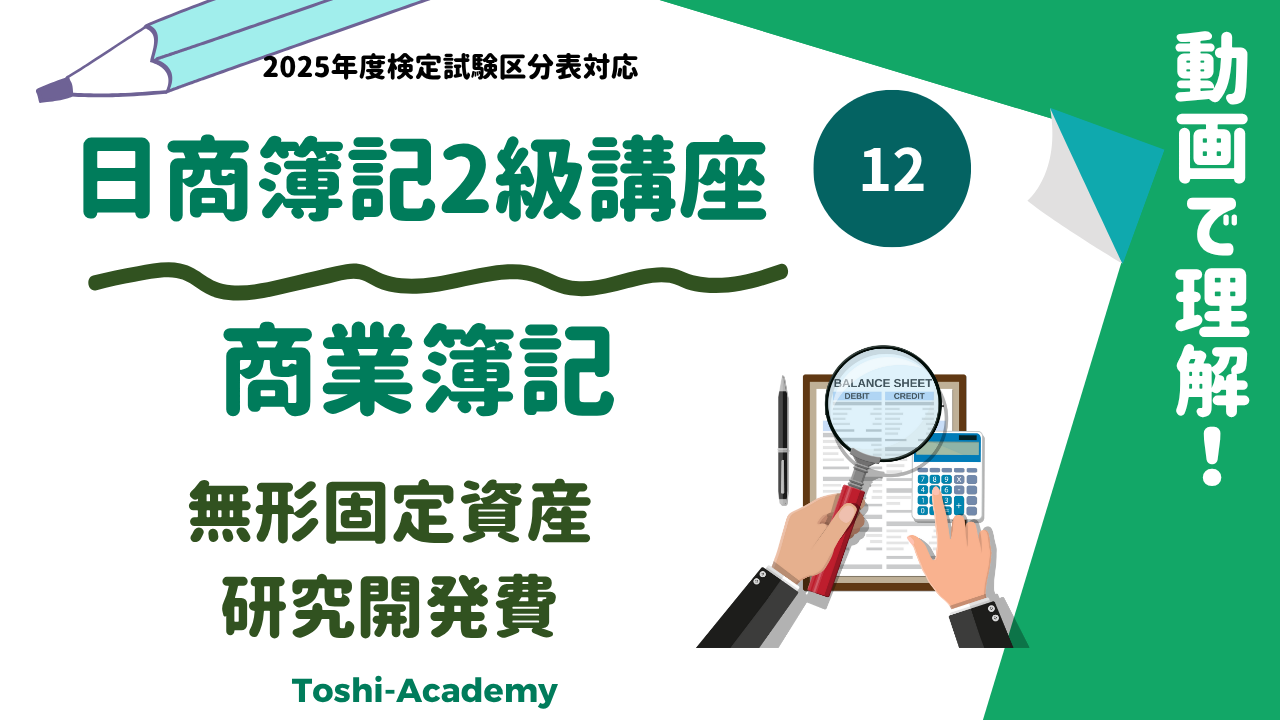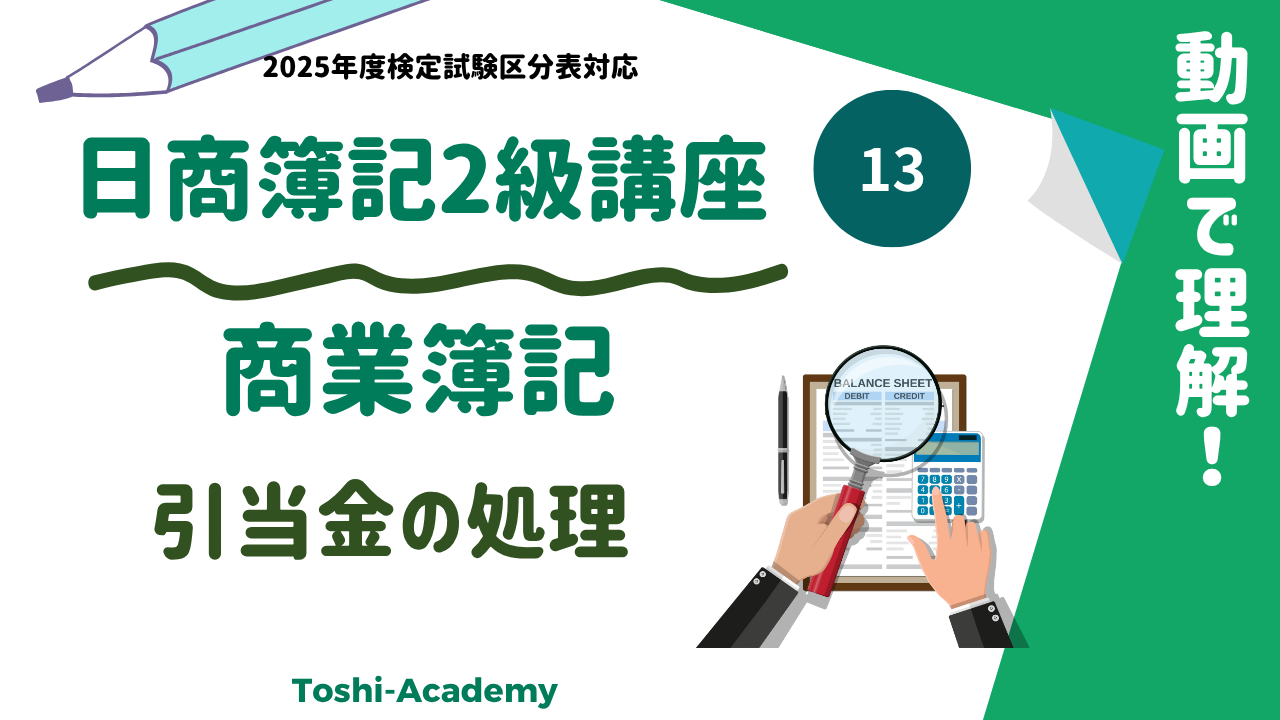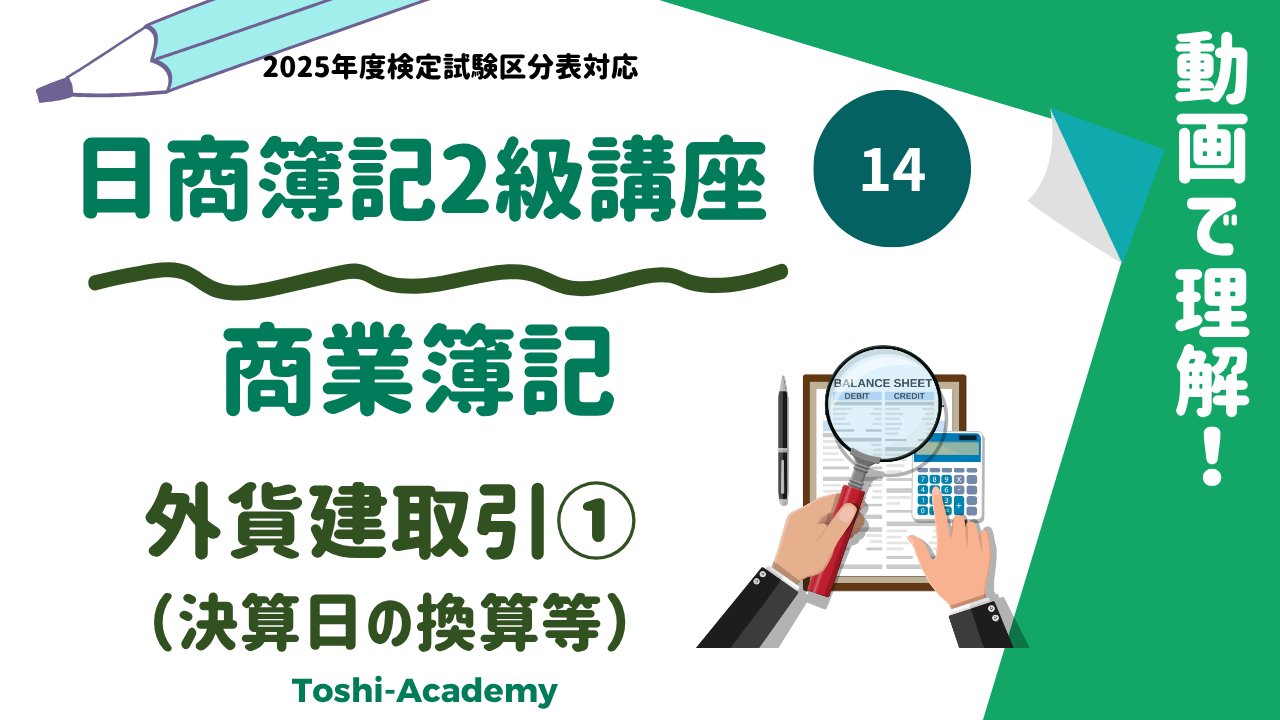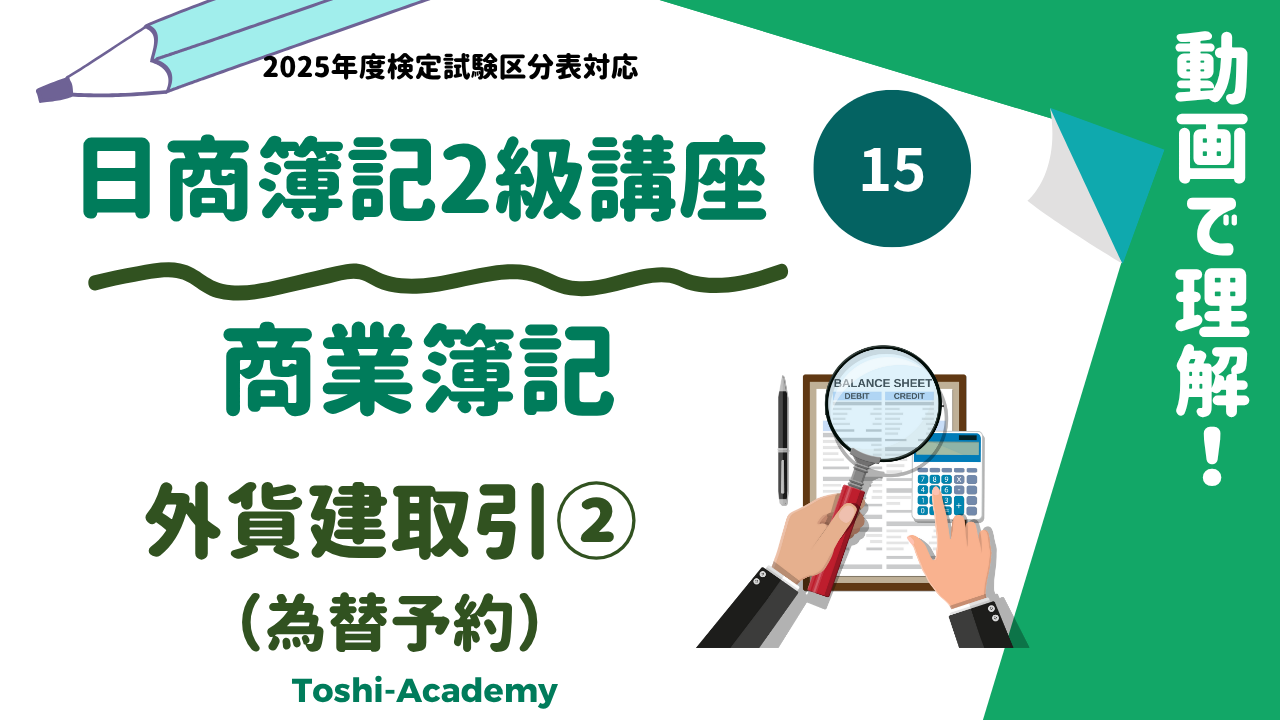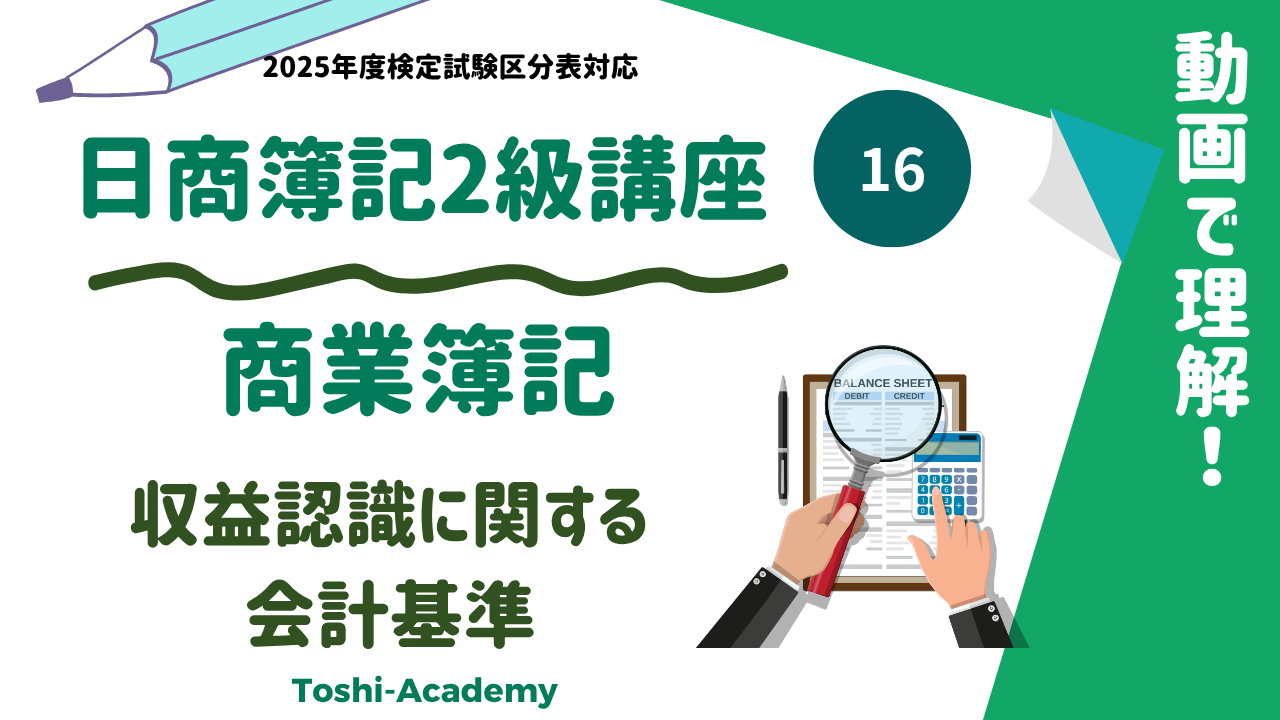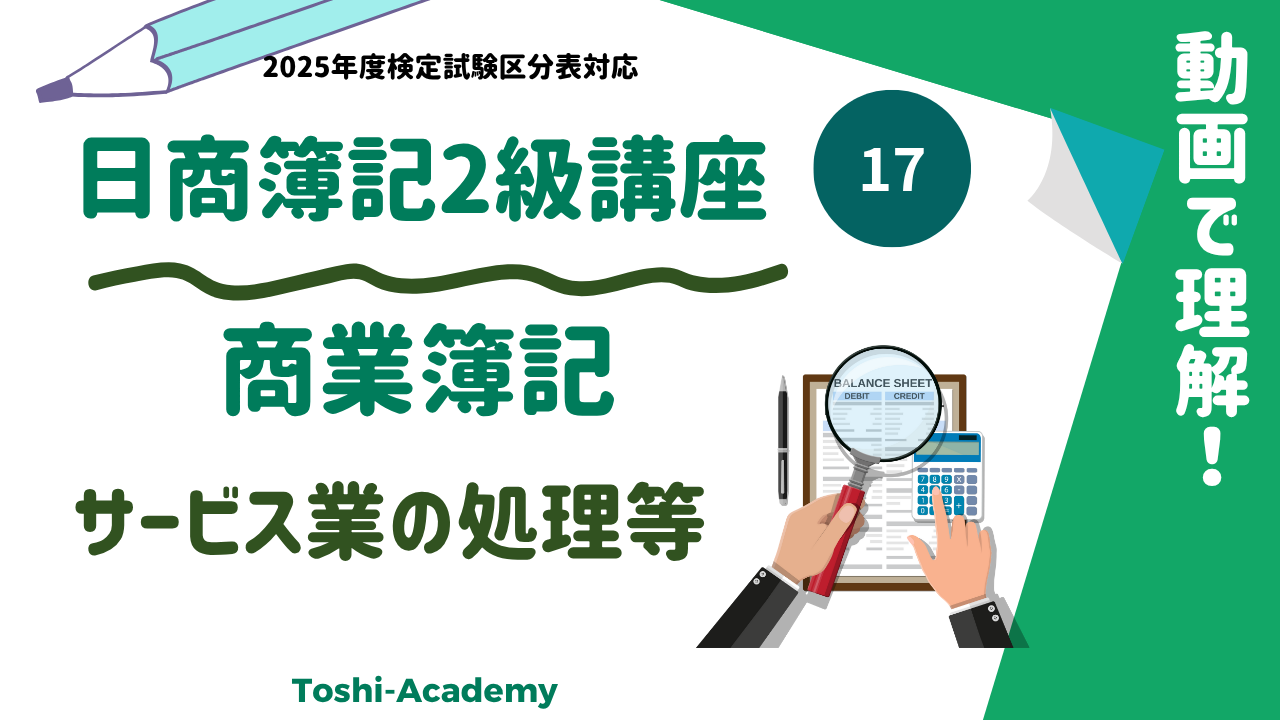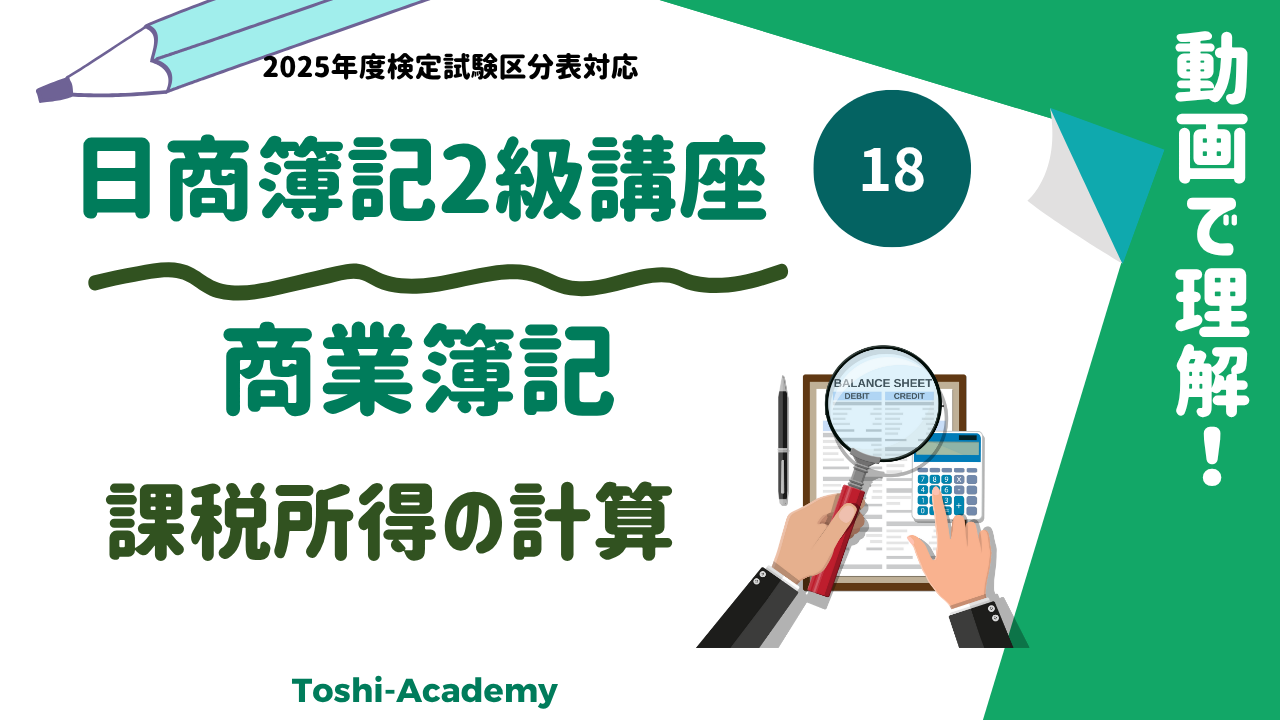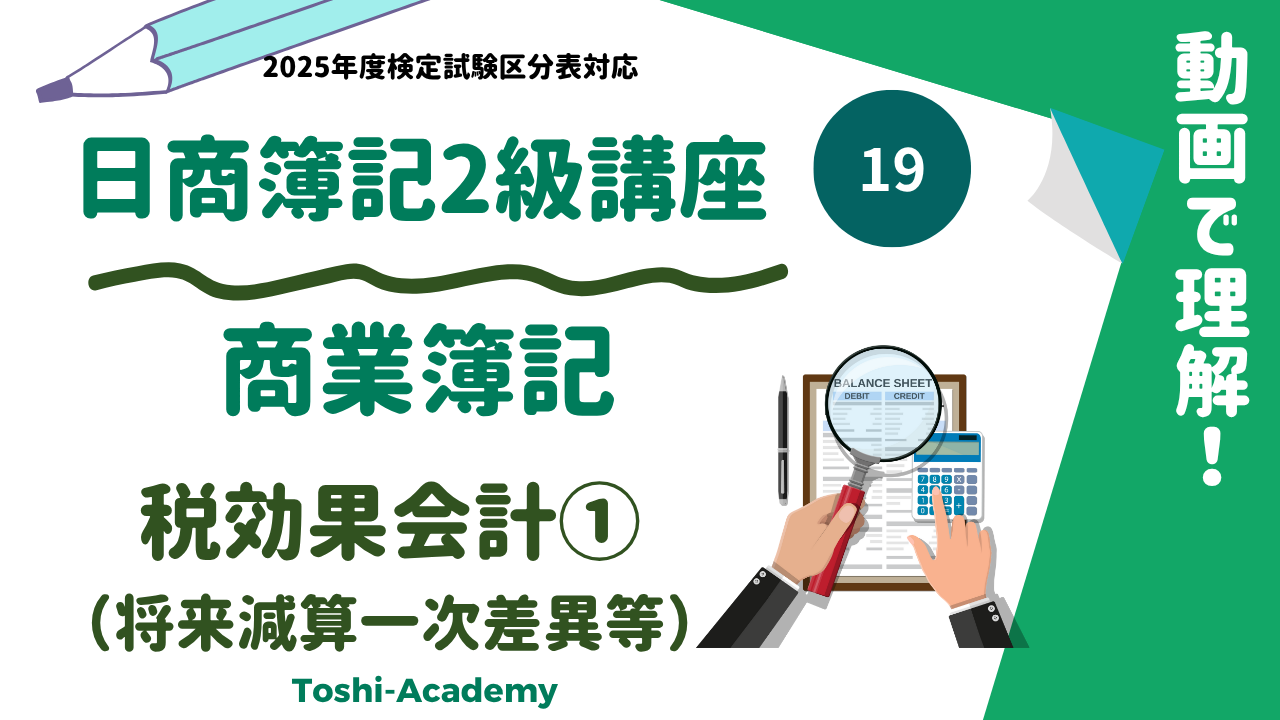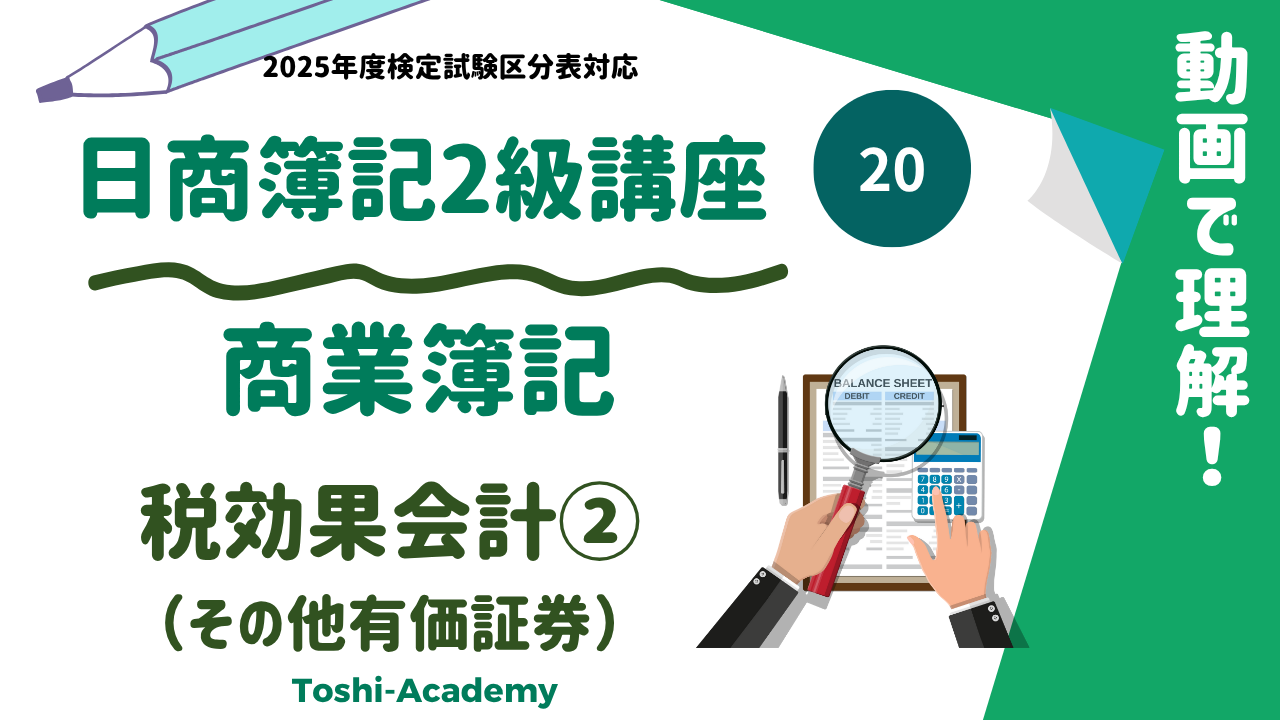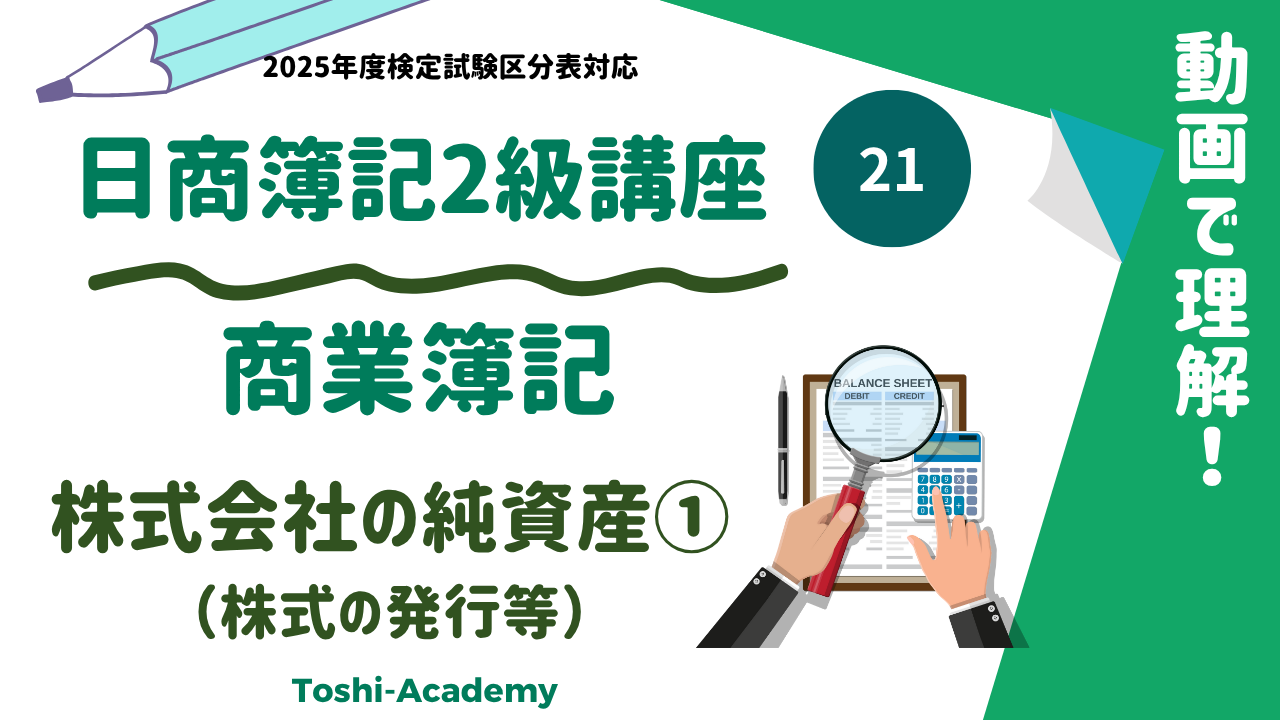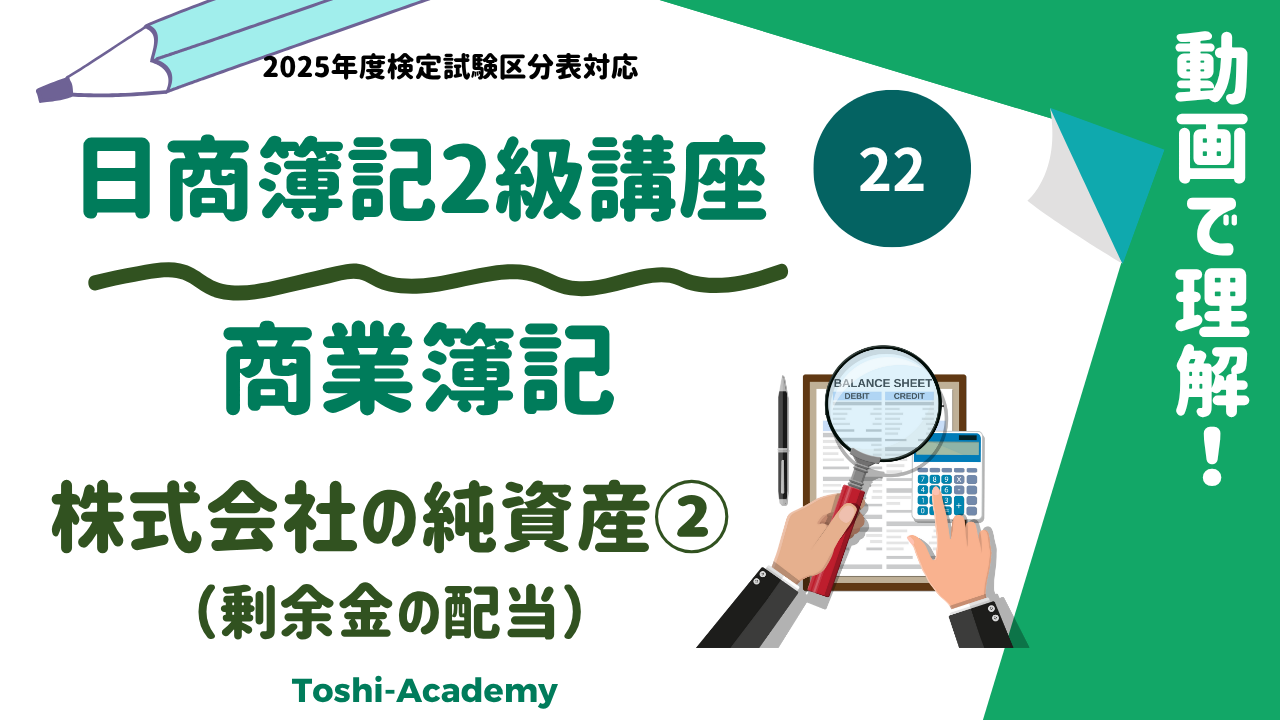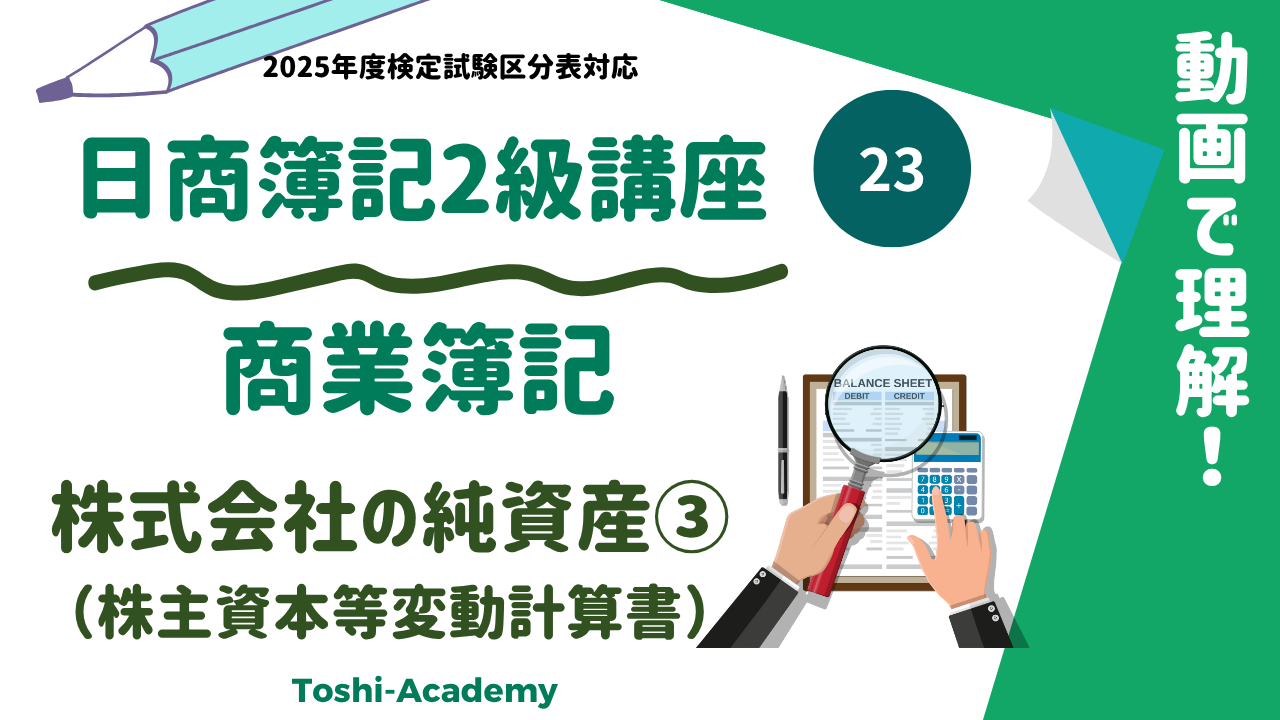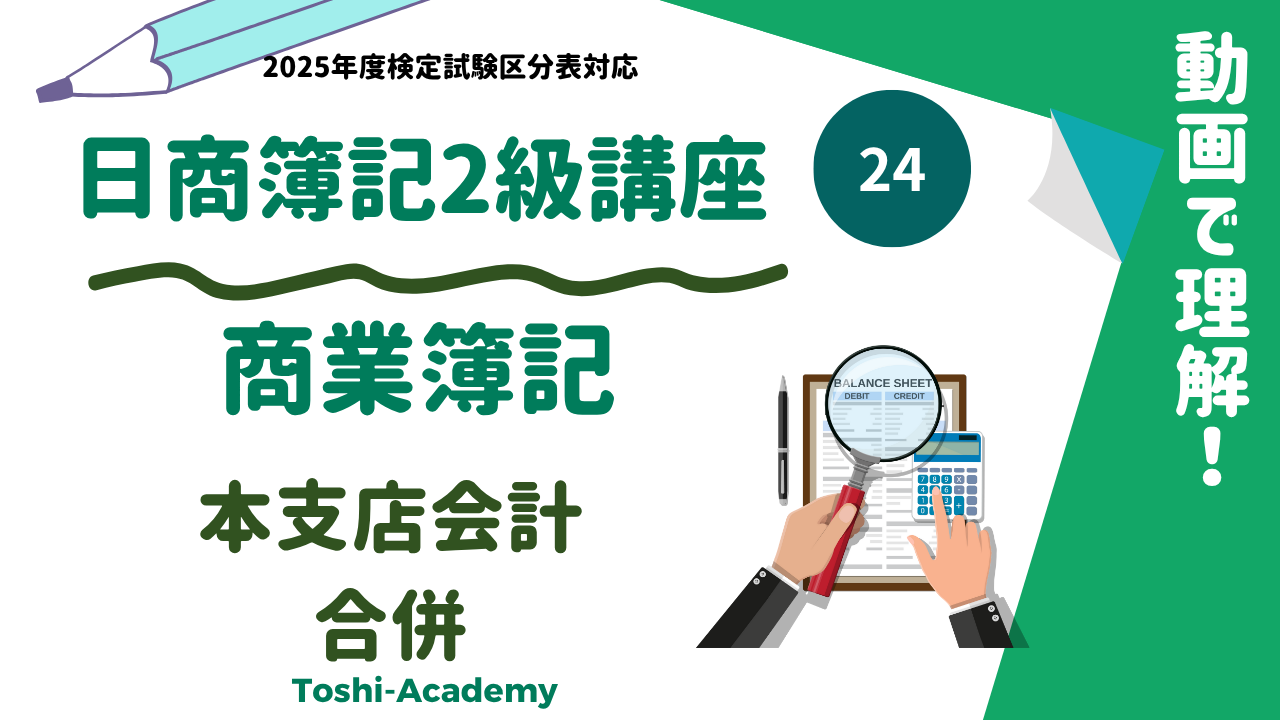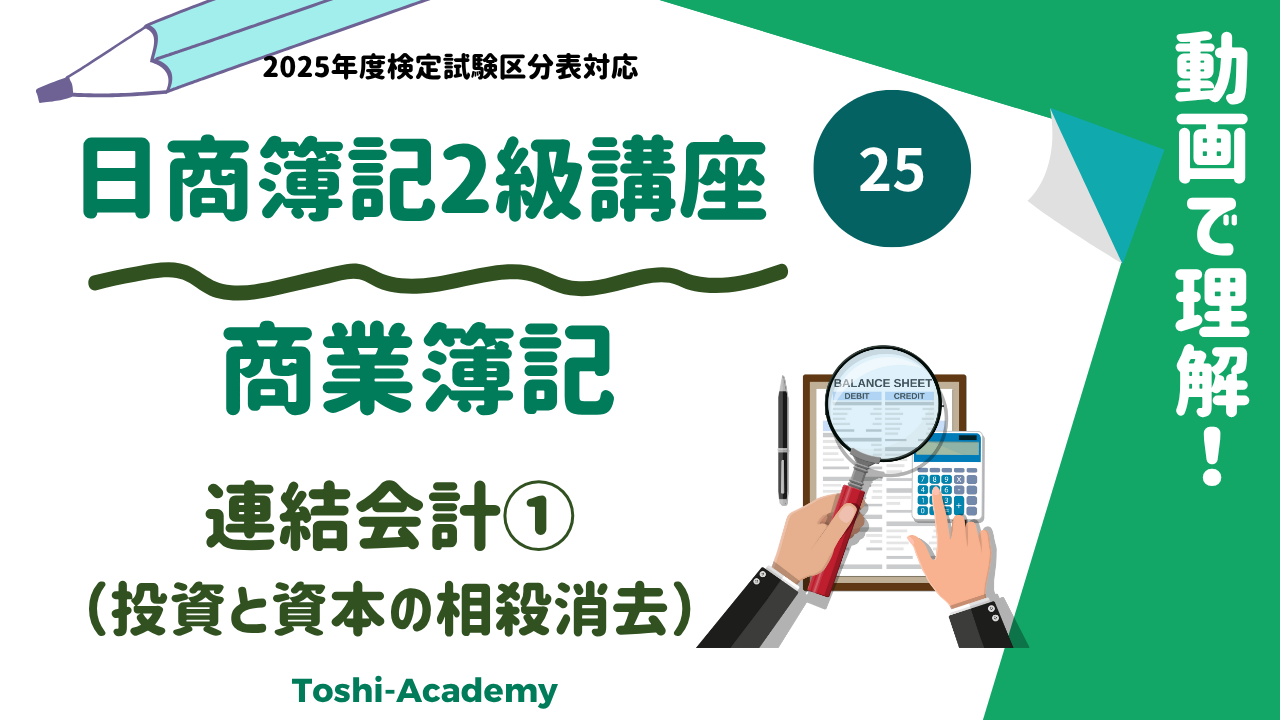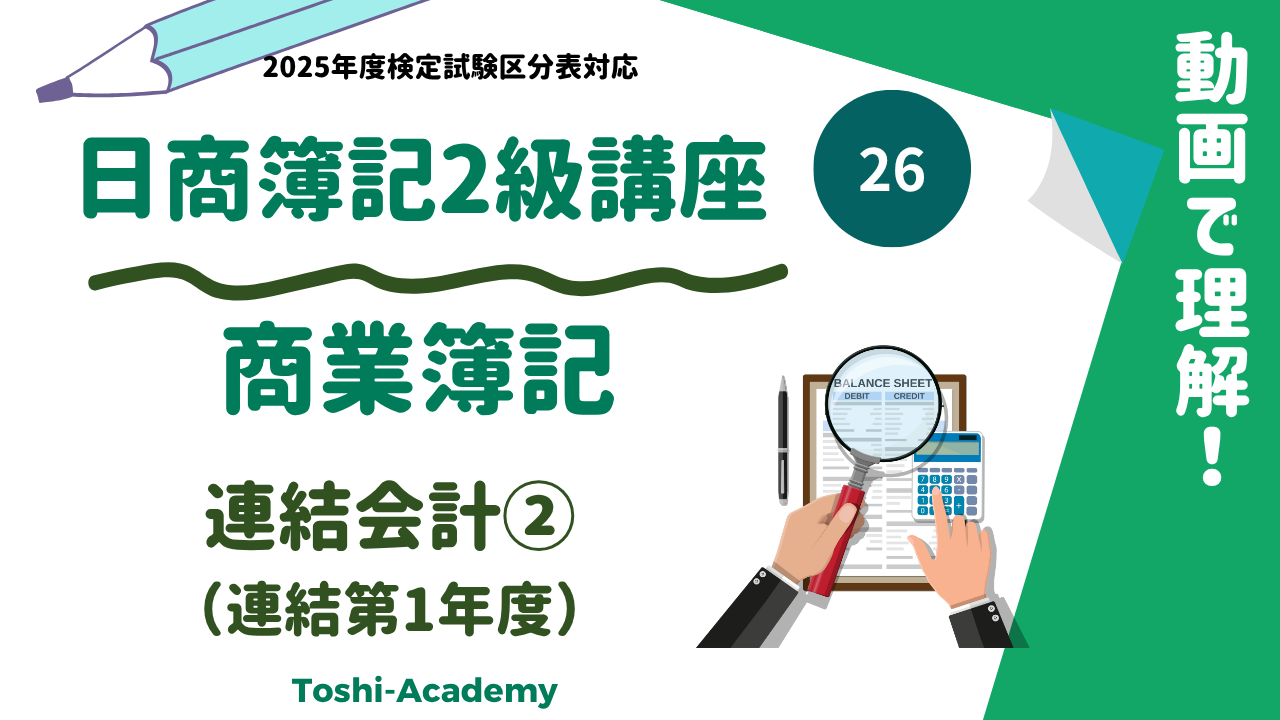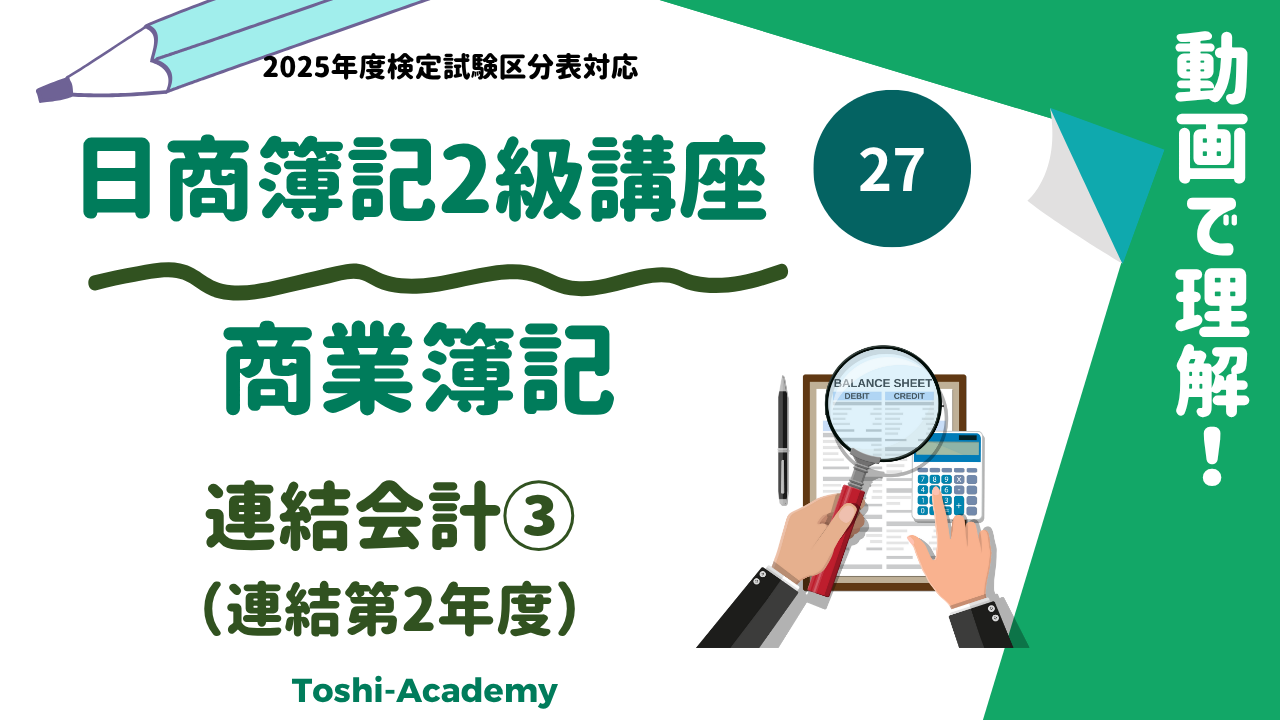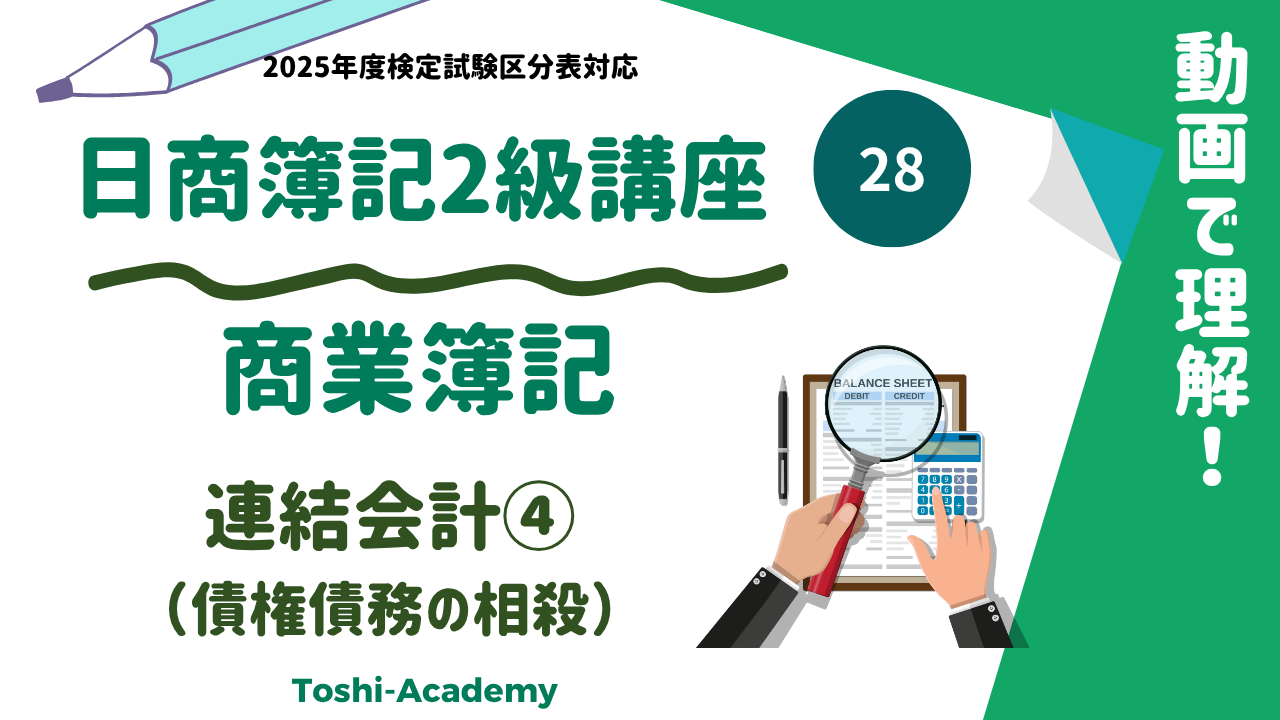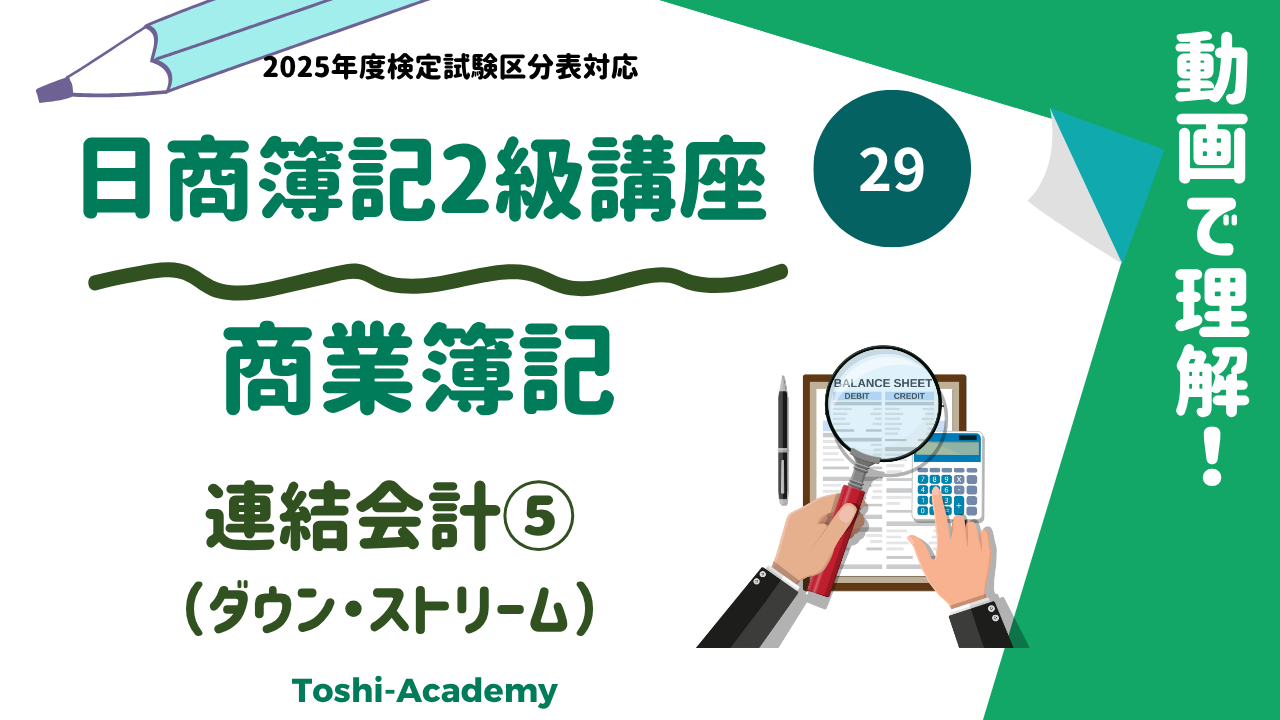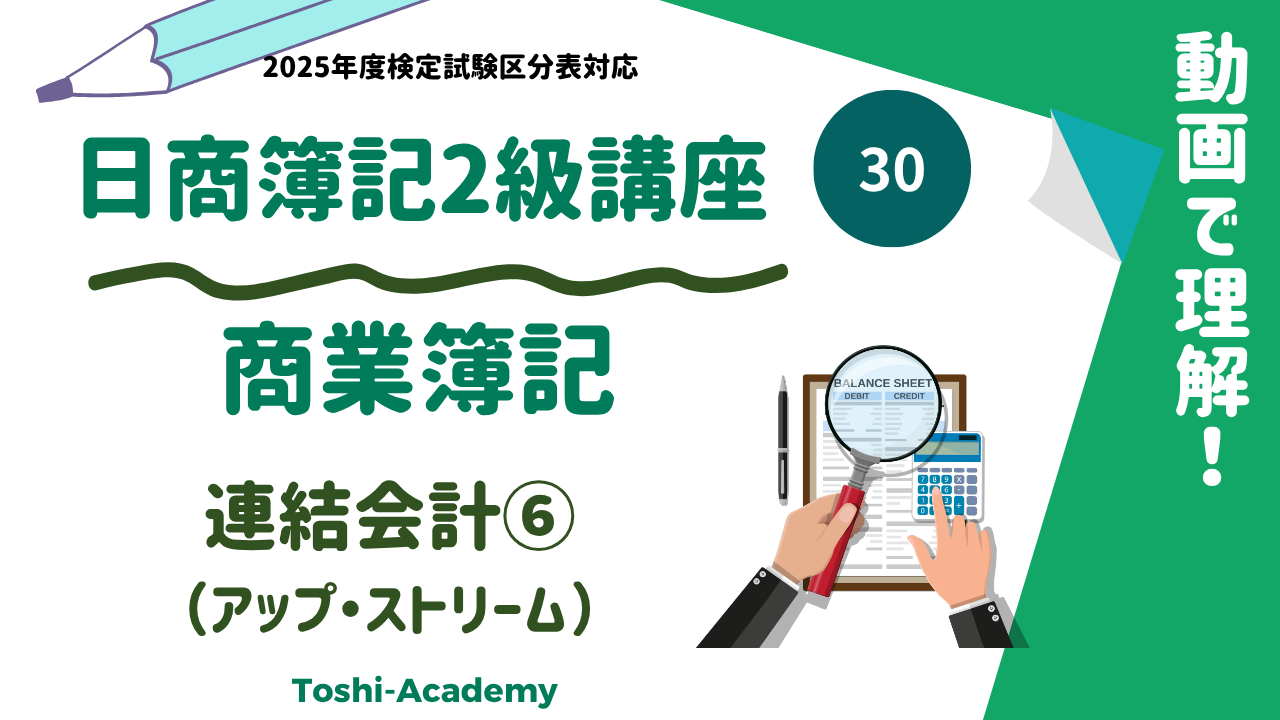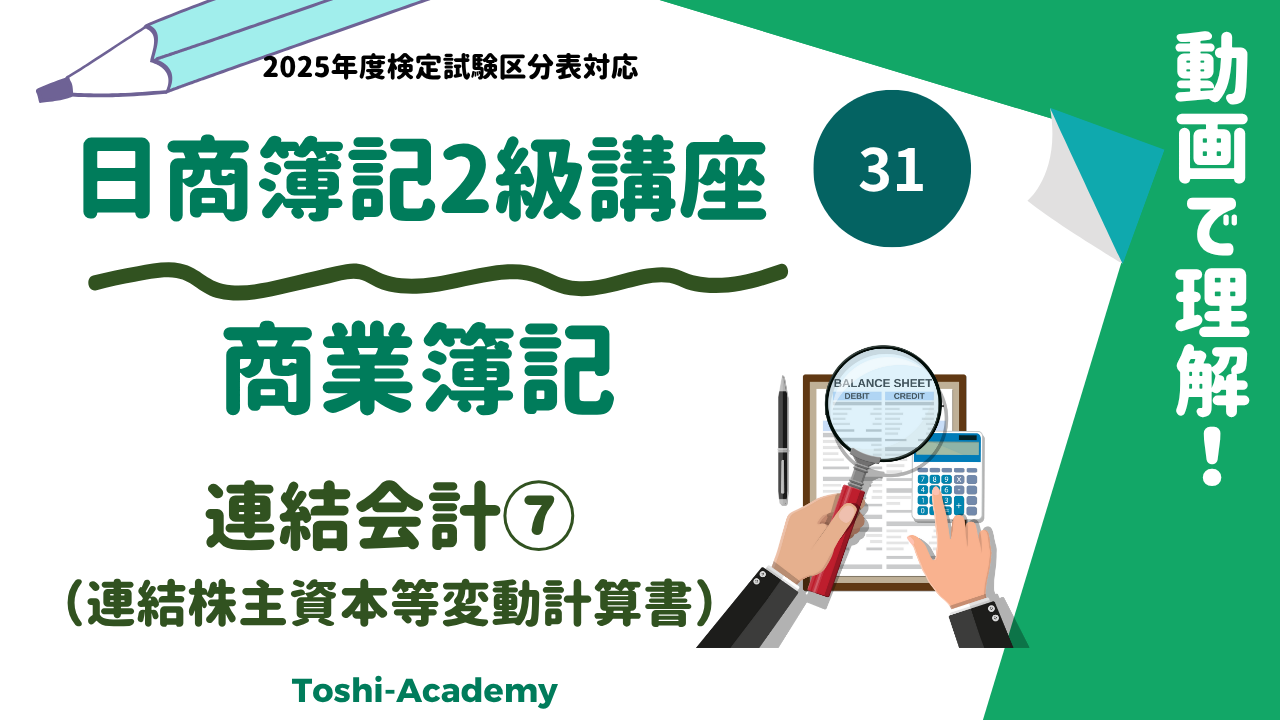簿記2級商業簿記
2023.04.11
図解でわかる!簿記2級商業簿記(全31回)
- 第1回 財務諸表
- 今回は、財務諸表について学習します。貸借対照表の資産の部は、流動資産と固定資産に分けて表示し、負債の部も、流動負債と固定負債に分けて表示します。損益計算書は、収益とそれに関連する費用を対応させることにより、売上総利益、営業利益、経常利益、税引前当期純利益とに分けて表示します。
- 第2回 商品に関する処理
- 今回は、商品に関する処理について学習します。簿記2級では、商品売買の処理として新たに売上原価対立法を学習します。また、決算日においては、実地棚卸を行い、在庫数量等を確認します。数量の減少については、棚卸減耗損a/cで処理し、時価の下落については、商品評価損a/cで処理します。
- 第3回 銀行勘定調整表
- 今回は、銀行勘定調整表について学習します。当座預金口座の残高と残高証明書の残高とが不一致の場合には、銀行勘定調整表により、不一致原因を確認し、両者の金額を一致させます。その際に必要な企業側の修正仕訳と銀行勘定調整表の3つの形式を確認しておきましょう。
- 第4回 債権債務
- 今回は、債権債務について学習します。手形取引、電子記録債権・電子記録債務に関する基本的な処理は、簿記3級で学習していますが、簿記2級では、手形等の譲渡、割引、不渡りに関する処理が新しく追加されます。各内容についての仕訳をしっかり理解してください。
- 第5回 有価証券①(購入・売却・端数利息等)
- 今回は、有価証券の購入と売却の処理を中心に学習します。有価証券を購入したときは、購入代価に付随費用を加算した取得原価で処理します。本試験では追加取得後の売却の問題が出題されることがあります。また、公社債を売却したときは、端数利息の処理が必要となります。端数利息に関する処理も本試験では必修です。
- 第6回 有価証券②(売買目的・支配目的・その他)
- 今回は、売買目的、支配目的、その他の有価証券の決算時の処理を中心に学習します。売買目的有価証券は、決算時に時価で評価し、評価差額については、有価証券評価損益a/cで処理します。支配目的の株式については、決算時に取得原価で評価し、その他有価証券は、決算時に時価で評価します。評価差額については、その他有価証券評価差額金a/cで処理します。
- 第7回 有価証券③(売買目的有価証券)
- 今回は、満期保有目的債券の処理を中心に学習します。満期保有目的債券は、原則として、取得原価によって貸借対照表価額とします。ただし、債券を債券金額より低い価額または高い価額で取得した場合において、その差額が金利の調整(金利調整差額)であるときは、償却原価法にもとづいて算定された価額(償却原価)を貸借対照表価額とします。
- 第8回 有形固定資産①(減価償却の方法)
- 今回は、有形固定資産の減価償却の方法を中心に学習します。簿記3級では、定額法という計算方法を学習しましたが、簿記2級では、定額法のほかに定率法、200%定率法、そして生産高比例法を学習します。また、記帳方法として間接法のほかに直接法も学習します。
- 第9回 有形固定資産②(除却・買換え・割賦購入等)
- 今回は、有形固定資産の除却、買換え、割賦購入等を中心に学習します。耐用年数到来前に、有形固定資産の本来の使用を止めて、その使用場所から取り除くことを除却といいます。買換えは、旧有形固定資産の売却と新有形固定資産の購入を同時に行うことです。固定資産を割賦購入した場合の利息の取扱いについても確認しましょう。
- 第10回 有形固定資産③(圧縮記帳)
- 今回は、圧縮記帳について学習します。国から地方自治体を通じて、特定事業の奨励のために企業に対して有形固定資産の購入資金を補助金として支給することがあります。受け取った補助金は収益として処理されるため、法人税等が課せられます。しかし、法人税等の課税の繰り延べを図ることを目的に税法が圧縮記帳の処理を認めています。
- 第11回 リース取引(ファイナンス・リース取引等)
- 今回はリース会計を学習します。リース取引は、ファイナンス・リース取引とオペレーティング・リース取引に分けることができます。ファイナンス・リース取引は、売買取引に準じて処理し、オペレーティング・リース取引は賃貸借取引に準じて処理します。ファイナンス・リース取引の中途解約についても確認しましょう。
- 第12回 無形固定資産・研究開発費(ソフトウェア等)
- 今回は無形固定資産と研究開発費について学習します。収益を獲得することを目的に長期にわたって使用する形のない資産を無形固定資産といいます。無形固定資産を取得したときは、取得原価で記帳し、決算日には、残存価額ゼロ、原則として定額法で償却し、直接法で記帳します。また、研究開発費は、発生時に費用として処理します。
- 第13回 引当金の処理(貸倒引当金等)
- 引当金とは、将来の特定の費用又は損失であり、その発生が当期以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつその金額を合理的に見積もることができる場合、当期の負担に属する金額を当期の費用又は損失として計上する際の貸方科目のことをいいます。
- 第15回 外貨建取引②(為替予約)
- 取引と同時に又は取引以前に為替予約を締結している場合は、先物為替相場による円換算額によって処理します。取引発生後に為替予約を締結した場合は、取引日の為替相場と先物為替相場の違いによって生じた差額を為替差損益a/cで処理します。
- 第16回 収益認識に関する会計基準
- 商品などを引き渡すことによって生じる対価受取りの権利に対して条件が付されている場合には、契約資産a/c(資産)で処理します。
2.商品などの引渡しが完了する前に受け取った対価については契約負債a/c(負債)で処理します。
- 第17回 サービス業の処理等
- 今回は、サービス業の会計処理を中心に学習します。サービス業では、サービスを提供したときに役務収益a/c(収益)で処理します。
- 第18回 課税所得の計算
- 今回は、課税所得の計算を中心に学習します。法人税、住民税及び事業税は、税法の考え方で計算された課税所得に一定の税率を掛けて計算します。
- 第19回 税効果会計①
- 今回は、税効果会計①として、将来減算一時差異の処理を学習します。繰延税金資産勘定や法人税等調整勘定を使いこなせるようにしましょう。
- 第20回 税効果会計②
- 今回は、税効果会計②として、その他有価証券の税効果会計を中心二学習します。将来加算一時差異として、繰延税金負債勘定を使いこなせるようにしましょう。
- 第22回 株式会社の純資産②
- 今回は、剰余金の配当についての処理を確認します。仕訳については、簿記3級で学習していますが、簿記2級では、株主総会時で決議される利益準備金の積立額を自分で計算しなければなりません。
- 第23回 株式会社の純資産③
- 今回は、株主資本等変動計算書を中心に学習します。株主資本等変動計算書は、純資産の期首残高、期中の変動額そして期末残高を記入することによって、主として株主資本の各項目の変動事由を明らかにすることを目的に作成されます。検定試験では、株主資本等変動計算書の作成問題が出題されることがあります。
- 第24回 本支店会計・合併等
- 今回は本支店会計と合併の処理を中心に学習します。本支店会計は、仕訳問題として出題されるほか、第3問で総合問題形式で出題されることもあります。支店勘定と本店勘定を使いこなせるようにしてください。合併は仕訳問題として出題されます。のれん勘定や負ののれん発生益勘定といった勘定科目に注意してください。
- 第26回 連結会計②(連結第1年度の処理)
- 今回は、連結第1年度の処理を中心に学習します。開始仕訳、のれんの償却、子会社利益の非支配株主持分への振替等、とても重要な仕訳を学習します。また、連結精算表の記入方法についても確認しましょう。
- 第27回 連結会計③(連結第2年度の処理)
- 今回は、連結第2年度以降の開始仕訳を中心に学習します。 連結第2年度以降の開始仕訳では、過年度の費用収益を利益剰余金に変えて処理します。タイムテーブルを使って開始仕訳を考える方法も確認します。
- 第28回 連結会計④(債権債務の相殺消去)
- 今回から成果連結と言われている期中の処理に関する連結修正を学習します。今回は債権債務の相殺の処理を中心に学習します。また、売掛金等を修正することによる貸倒引当金の調整についても確認しましょう。
- 第30回 連結会計⑥(アップ・ストリーム)
- 子会社が親会社に商品等を販売することをアップ・ストリームといいます。子会社が親会社に商品を販売し、その商品が親会社の期末商品として残っている場合、子会社が付加した利益(未実現利益)は、連結上、消去され、非支配株主持分の調整が必要となります。
- 第31回 連結会計⑦(連結株主資本等変動計算書)
- 今まで学習してきた連結会計では連結株主資本等変動計算書の存在を無視してきました。今回、連結株主資本等変動計算書を取り上げますが、新たな連結修正仕訳が出てくるわけではありません。仕訳をする上で科目名が変わる点に注意してください。
PAGE TOP